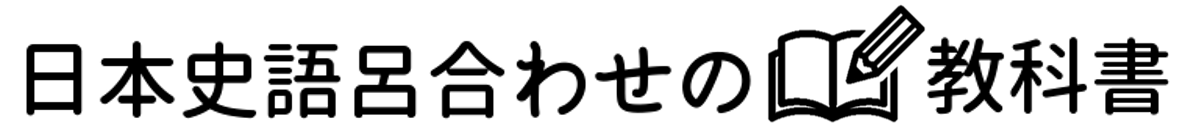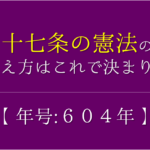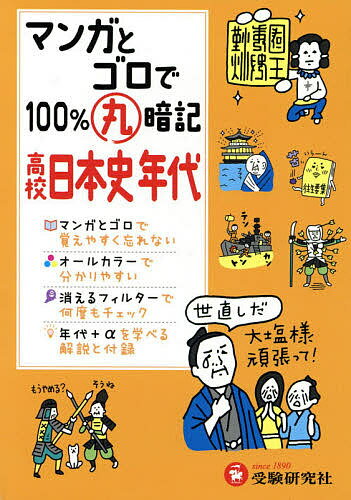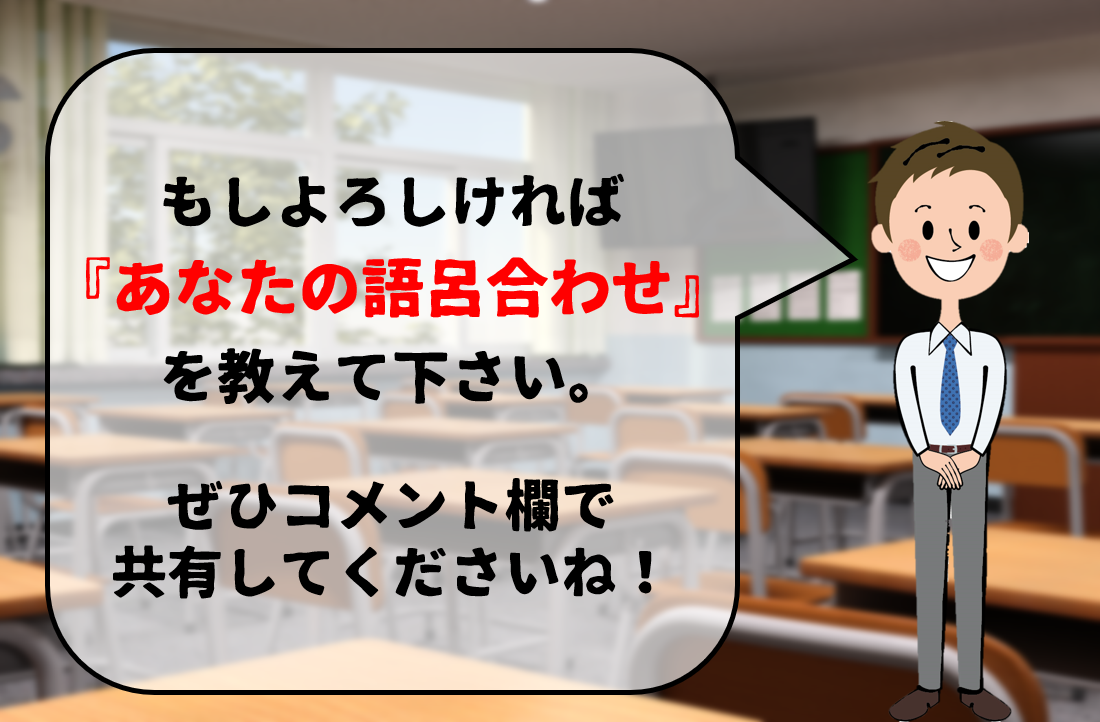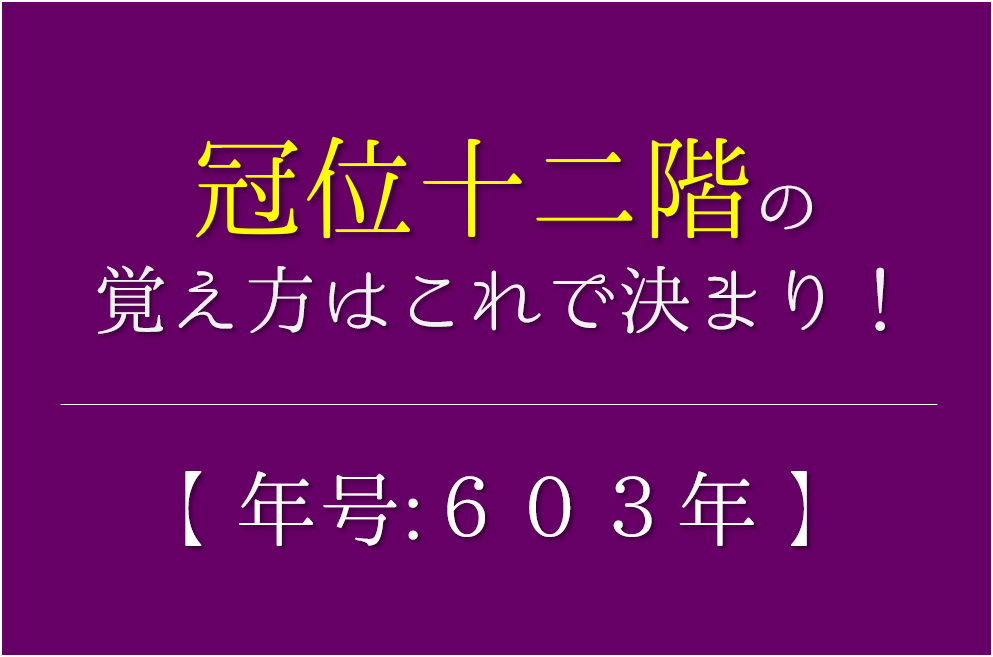
家柄などにこだわらず有能な人材を登用することは今では当たり前ですが、古代社会でも貴族以外からも有能な人材を確保しようとした制度があります。
以前は聖徳太子が定めた制度とされていましたが、現在では蘇我馬子が中心となって作ったのではないかと言われている「冠位十二階」です。
今回はそんな冠位十二階の概要・年号の覚え方(語呂合わせ)についてご紹介します。
目次
冠位十二階とは?
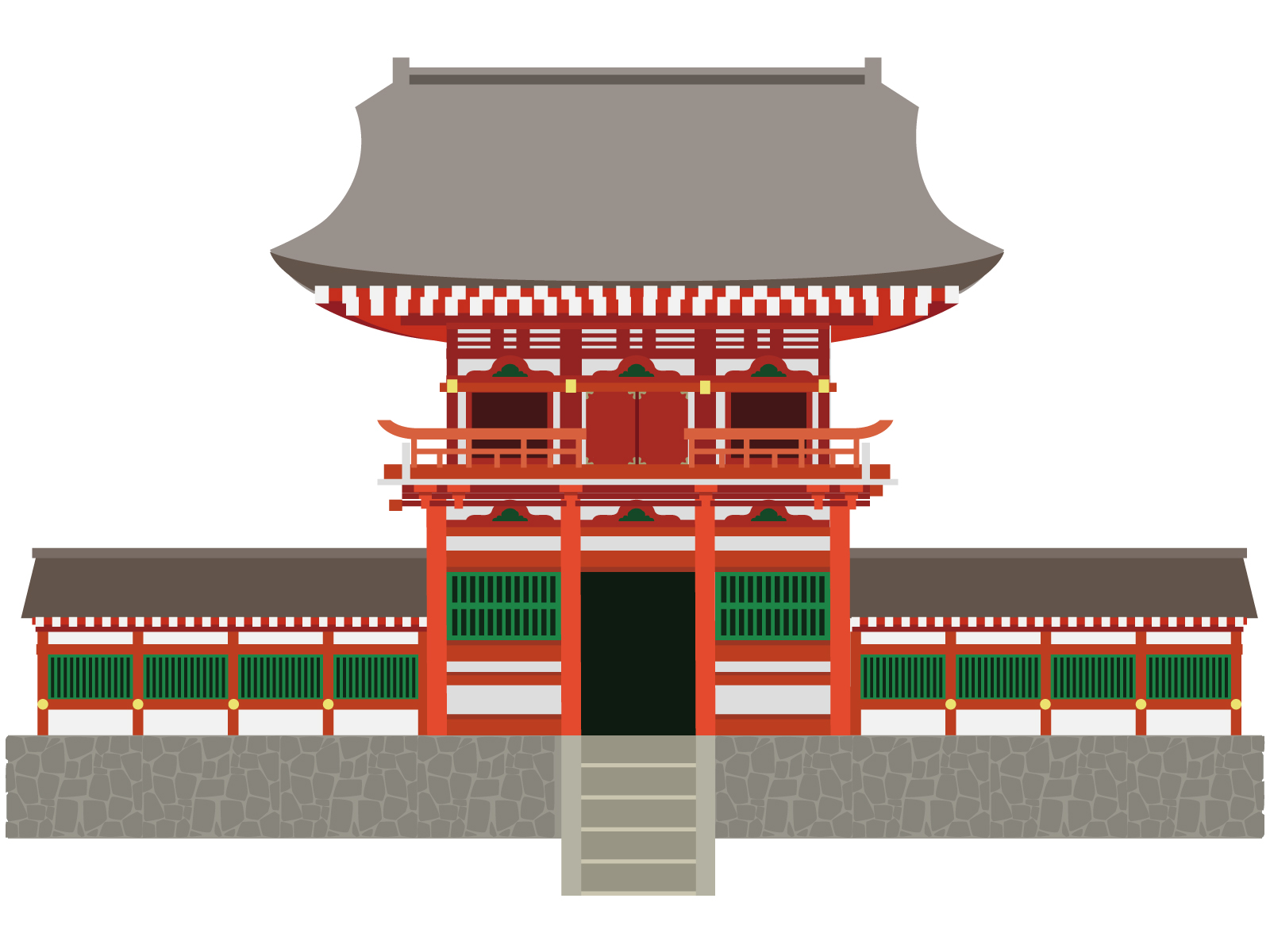
冠位十二階とは、603年に制定された企業や官庁の役職のような身分制度です。
色の違う絹でできた冠によって、階級の違いがわかるようになっていました。
冠位十二階を定めた目的の一つは、諸外国との外交上の問題です。
外交相手である高句麗・新羅・百済や中国に官僚制度があり、それらの国々と応対するためのわかりやすい序列によって、相手への対応の状態を伝えることができました。
さらにそれまでの氏姓制度の場合、個人に授けられる位ではないため役人のような上下関係を明確に表すことができませんでした。
しかし、冠位十二階では生まれによる身分ではなく役職を与えることができたため、職務上の上下関係を結ばせることに役立ちました。
◆冠位十二階の色と順番
最も有力な説は、儒教の五常がもとになっている「五行五色説」で、大徳・小徳・大仁・小仁・大礼・小礼・大信・小信・大義・小義・大智・小智の順になっていて、徳は紫または錦、仁は青、礼は赤、信は黄、義は白、智は黒となっています。
徳を最上に置いたのは仁以下の5つを合わせた物であるためと、聖徳太子伝暦では伝えています。
結果として、冠位十二階を定めたことによるメリットは何だったのでしょうか?
冠位十二階や十七条の憲法で国家としての形を整えることによって、遣隋使を派遣したときに隋のような大国と日本が対等であることを近隣諸国に印象づけることができたと言えます。
また、出自に関係なく有能な人々に重要な職についてもらうことは、国家にとってプラスでしょう。
【冠位十二階の語呂合わせ】年号(603年)の覚え方!

冠位十二階の語呂合わせ①
無縁(60)だけど、さ(3)あ頑張ろう!冠位十二階
今までは出世に縁のなかった身分の人にもチャンスがやって来ました。
冠位十二階の語呂合わせ②
無礼(60)はせずに、目指せ冠位の座(3)
出世のためでも節度はわきまえたいものです。
冠位十二階の語呂合わせ③
群れ(60)見(3)ぬ冠位十二階
冠位十二階という注目された新制度にも、群衆は見当たりません。
冠位十二階の語呂合わせ④
無礼(60)にならないように身(3)分をハッキリ!
諸外国の方達に身分がわかりやすいことは大切です。
冠位十二階の語呂合わせ⑤
禄を(60)授(3)かる冠位十二階
禄(ろく)とは官に仕える者に下付される給与のことです。
以上、冠位十二階の語呂合わせでした!