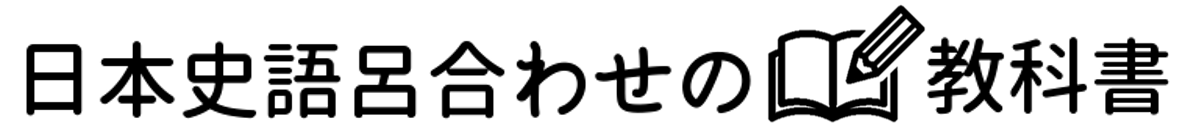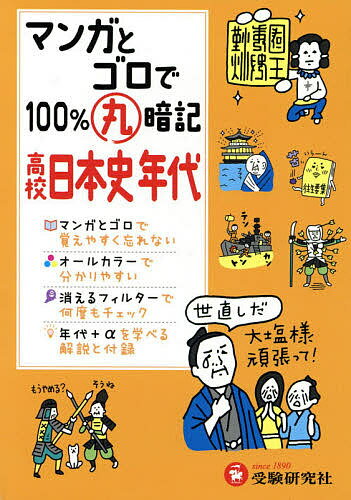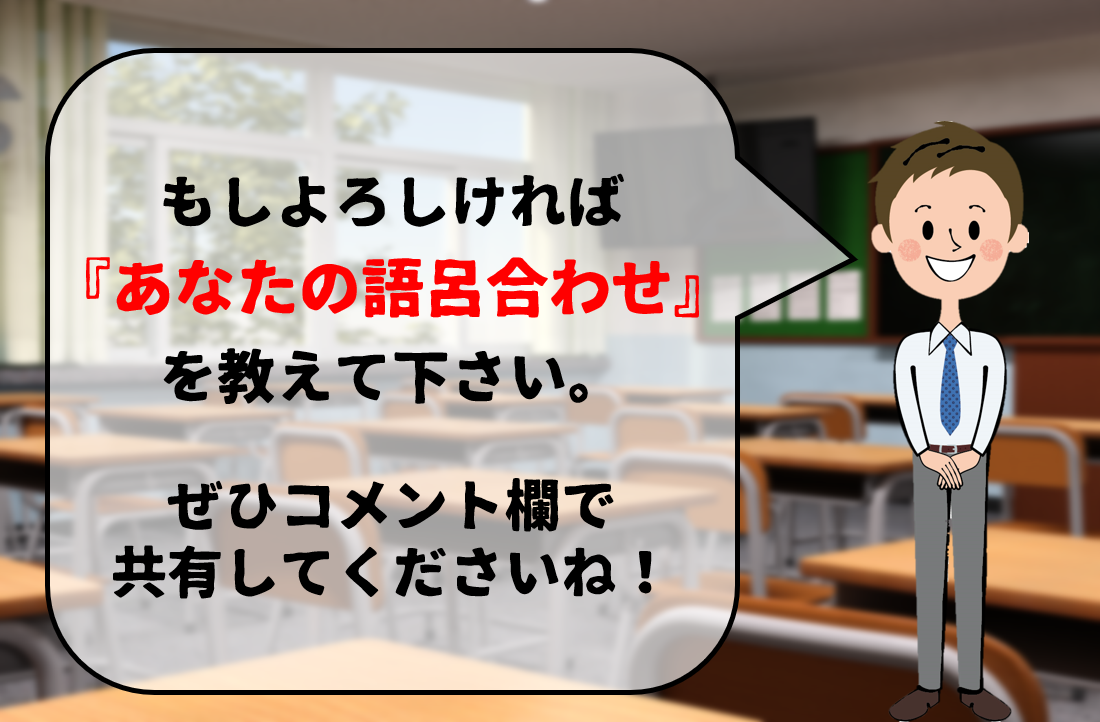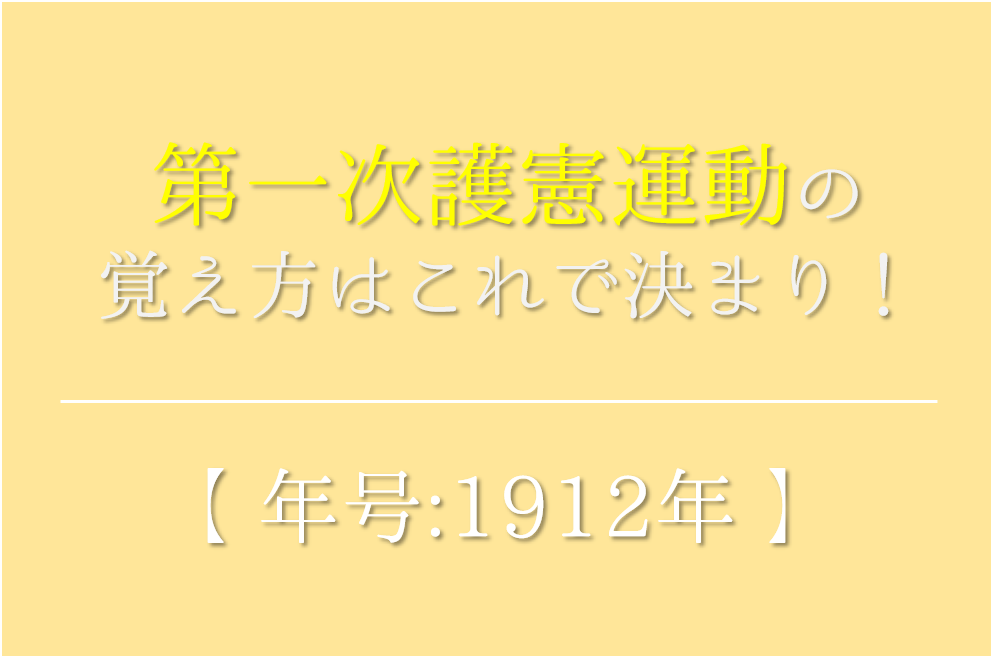
明治から大正時代、当時の日本の政治は藩閥政治と呼ばれ、9人の実力者に牛耳られていました。
しかし、この政治体制を批判し民主的な政治を希望する人が徐々に増えてきます。
そして1912年、議会中心の政治を望む勢力などにより「閥族打破・憲政擁護」をスローガンとした第一次護憲運動が起こりました。
今回はこの第一次護憲運動の概要・年号の覚え方(語呂合わせ)についてご紹介します。
目次
第一次護憲運動とは?

第一次護憲運動とは、1912年(大正元年)に起こった「閥族打破・憲政擁護」をスローガンに掲げ、議会中心の政治を望む人々により起こった暴動です。
当時の日本は元老(山縣有朋、井上馨、松方正義、西郷従道、大山巌、西園寺公望、桂太郎、黒田清隆、伊藤博文ら9名)が政治の中心となり、藩閥政治が行われていましたが、この体制を批判する声も徐々に増えていきます。
そんな中、陸軍大将であった桂太郎が第三次桂内閣を組閣したことを、陸軍の軍備拡張に関係するとみなした反発勢力が立ち上がります。
立憲国民党の「犬養毅」、立憲政友会の「尾崎行雄」らが互いに協力し、憲政擁護会を結成。遂に第一次護憲運動が起こりました。

(左:犬養毅 右:尾崎行雄)
この運動により、議会で桂内閣の不信任案が提案されますが、桂はこれを避ける為5日間の議会停止を命じます。
しかしこの判断が国民の怒りを買い、議員への暴行事件などに発展。
その後も憲政擁護会は東京の神田や上野などで桂内閣を批判する集会を開く、警察や国民新聞社を襲撃するなど激しい運動を行います。
国民の怒りは東京に留まらず、関西など各地での暴動に広がり、桂内閣は総辞職を余儀なくされました。
その後組閣した山本権兵衛内閣が国民に融和的な政治・政策をとっていることから、第一次護憲運動が日本の政治に大きな影響を与えたと言えるでしょう。
【第一次護憲運動の語呂合わせ】年号(1912年)の覚え方!

第一次護憲運動の語呂合わせ①
行く(19)よ否認(12)に第一次護憲運動
桂内閣を批判する運動が各地で行われました。
第一次護憲運動の語呂合わせ②
第一次護憲運動で内閣が引く(19)のはいつ(12)だ?
桂内閣の総辞職を願う声が多くありました。
第一次護憲運動の語呂合わせ③
一級(19)の人間に一任(12)するな!第一次護憲運動
たった9名が日本の政治を動かすなんて恐ろしいですよね…
第一次護憲運動の語呂合わせ④
第一次護憲運動で行く(19)ぞ、悲痛(12)な声を届けに
国民の怒りの叫びは暴動に形を変えました。
第一次護憲運動の語呂合わせ⑤
行く?(19)いつ?(12)第一次護憲運動
集会に暴行事件、襲撃など多くの国民が参加しました。
以上、第一次護憲運動の語呂合わせでした!