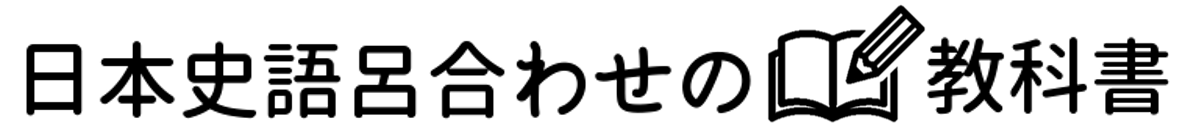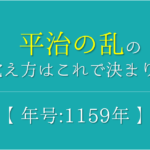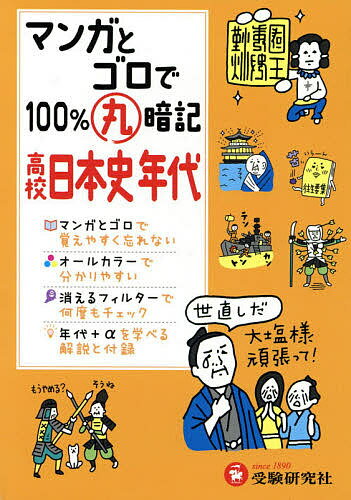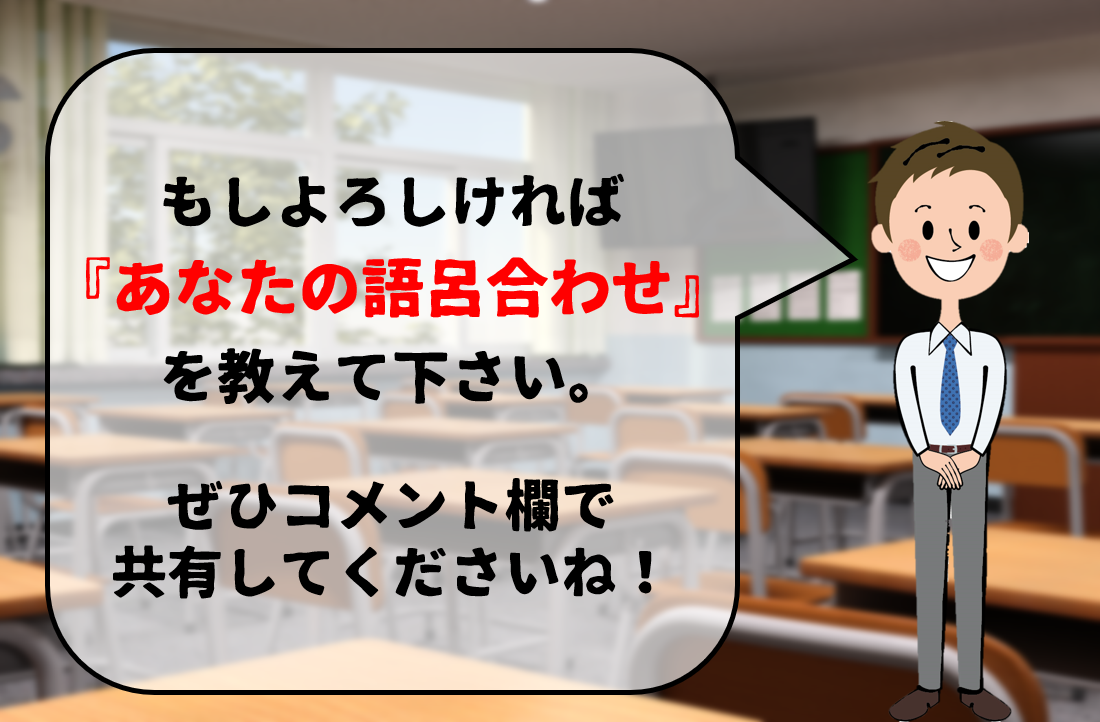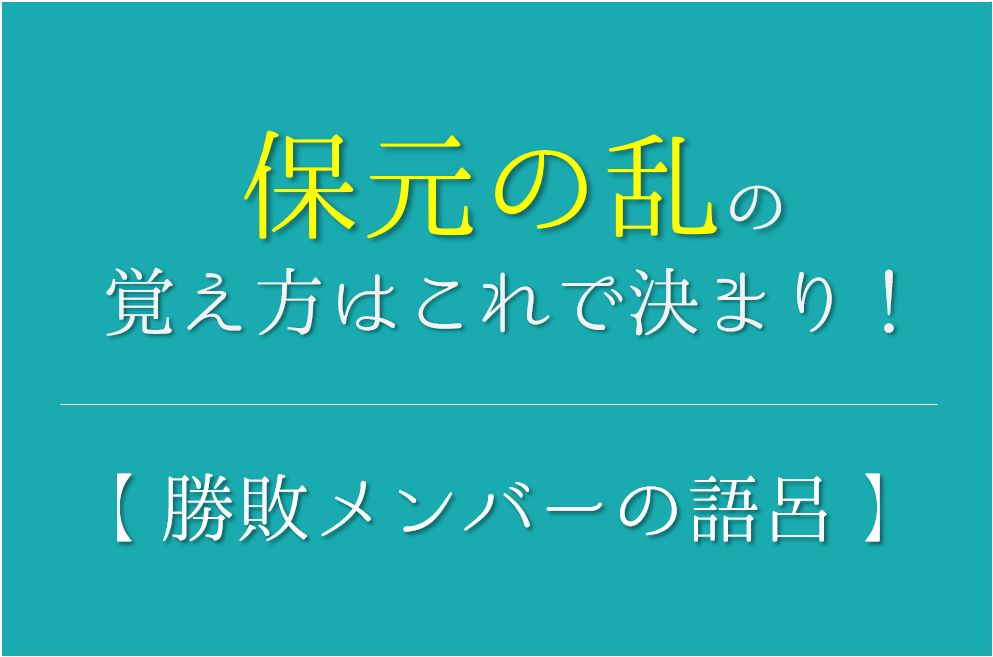
平安時代末期、白河天皇は8歳の堀河天皇に譲位して、上皇として政治の実権を握りました(1086年、院政)。
白河上皇→鳥羽上皇(白河上皇の孫)→後白河上皇と、上皇が政治を執り行う院政が続き、天皇と上皇が両立することになります。
そんな中、崇徳上皇と後白河天皇が政権を争います。
上皇側と天皇側それぞれに貴族・武士がつき、保元の乱という騒乱になりました。
今回はそんな保元の乱の勝敗メンバーの覚え方(語呂合わせ)とその概要をご紹介します。
目次
保元の乱とは?

(保元・平治の乱合戦図屏風絵 出典:Wikipedia)
保元の乱とは、1156年 崇徳上皇と後白河天皇とが朝廷政治の実権を争っておこった戦乱のことです。
崇徳上皇と後白河天皇それぞれに貴族や武士が味方をして、権力闘争だけでなく、京の都で実際の戦闘がおこりました。そして、後白河天皇が勝ち、負けた崇徳上皇は讃岐(今の香川県)へ流されました。
以下、天皇側、上皇側の各陣営についた人物をまとめます。( )内はそれぞれの関係です。
| 勝ち | |
| (弟)後白河天皇(ごしらかわてんのう) | 天皇家 |
| (兄)関白:藤原忠道(ふじわらのただみち) 藤原信西(ふじわらのしんぜい) |
藤原家 |
| (甥)平清盛(たいらのきよもり) | 平氏 |
| (子、兄)源義朝(みなもとのよしとも) | 源氏 |
| 負け | |
| (兄)崇徳上皇(すとくじょうこう) | 流罪 |
| (弟)左大臣:藤原頼長(ふじわらのよりなが) | 戦死 |
| (叔父)平忠正(たいらのただまさ) | 斬首 |
| (父)源為義(みなもとのためよし) (弟)源為朝(みなもとのためとも) |
斬首 流罪 |
負けた崇徳上皇側についた人たちは、斬首、流罪に処せられました。
保元の乱の勝利後、後白河天皇は二条天皇(後白河天皇の皇子)に位を譲り、上皇となります。
そして後白河上皇の側近である藤原信西が戦後処理を取り仕切りました。信西の妻は後白河天皇の乳母で、信西は後白河天皇と近かったのです。
信西の戦後処理は厳しいもので、源義朝は負けた側の父・為義を自ら斬首させられます。
また、信西は平清盛に恩賞を厚くしています。
これにより源義朝は信西に強い不満を抱きます。
そして信西と敵対していた藤原信頼(ふじわらののぶより)と手を組んで、3年後に平治の乱(1159年)をおこします。
【保元の乱の覚え方】メンバーの語呂合わせ

保元の乱の語呂合わせ①
ゴジラが西の道を友とぜいぜいあるき、すっと長いため池にとどまった
ゴジラ(後白河)が西(信西)の道(忠道)を友と(義朝)ぜいぜい(清盛)あるき、すっと(崇徳)長い(頼長)ため池(為義)にとどまった(ただまった→忠正)
保元の乱の語呂合わせ②
勝ったゴジラは正義の道を信じ、負けたスドーのより長い忠誠を試す
勝ったゴジラ(後白河)は正義(正(せい)→清盛、義→義朝)の道(忠道)を信(信西)じ、負けたスドー(崇徳)のより長い(頼長)忠誠(忠正)を試す(ためす→為→為義)
保元の乱の語呂合わせ③
頼りないためにただ負けた崇徳上皇。どうしと朝盛った?勝った後白河天皇。
頼りない(頼長)ため(為義、為朝)にただ(忠正)負けた崇徳上皇。どう(忠道)し(信西)と朝(義朝)盛った(清盛)?勝った後白河天皇。
保元の乱の語呂合わせ④
忠道信西/清盛/義朝(ちゅうどうしんぜいせいぜいぎちょう)、頼長/忠正/為義為朝(らいちょうちゅうせいしぎしちょう)
藤原家/平氏/源氏、の順番で名前を並べました。それを音読みして覚えていくのも一つの手です。
保元の乱の語呂合わせ⑤
朝は西市、繁盛してるね。まさそのために寄ったの。
朝(義朝)は西(信西)市(いち→みち→忠道)、繁盛してるね(清盛)。まさ(忠正)そのために(為義為朝)寄ったの(頼長)。
以上、保元の乱の勝敗メンバーの語呂合わせでした!