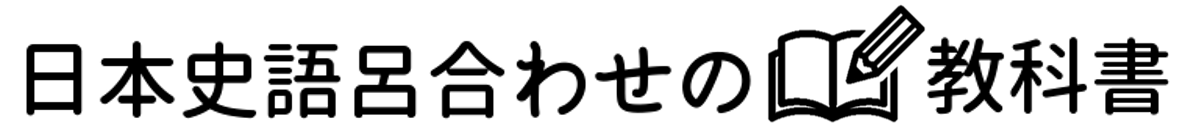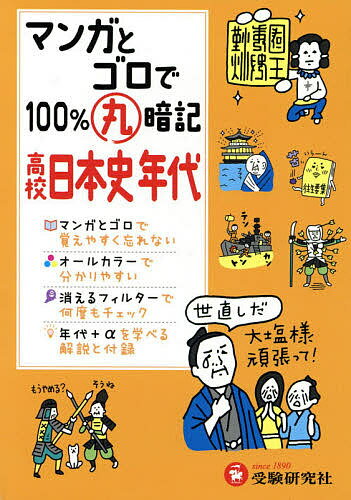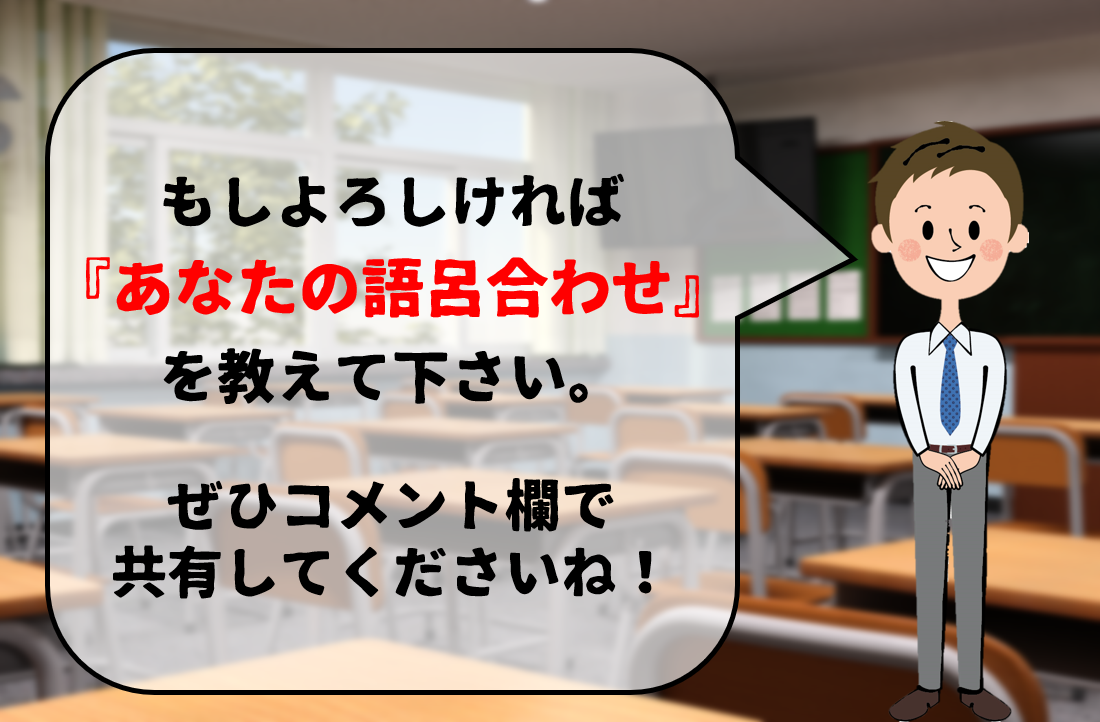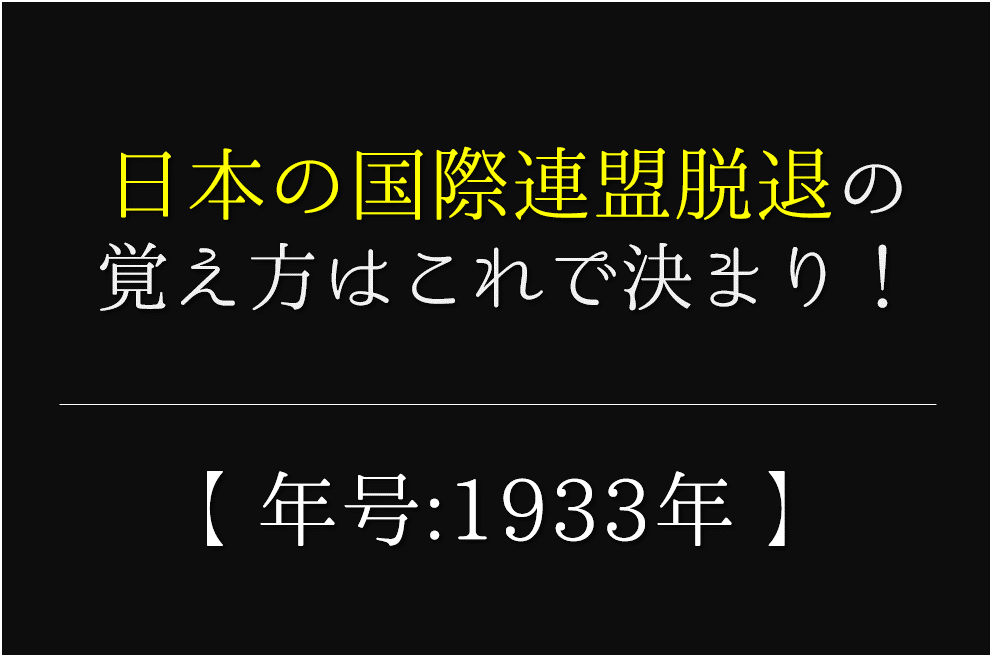
1920年1月に発足した史上初の国際平和機構である国際連盟。
日本は創立以来、常任理事国や事務局次長を務めるなど中核的な役割を担っていました。
しかし、満州事変を機にその立場は一変。諸外国から非難を受けることになり、1933年(昭和8年)に日本は国際連盟を脱退しました。
今回はこの日本の国際連盟脱退の概要・脱退年号の覚え方(語呂合わせ)についてご紹介します。
目次
日本の国際連盟脱退とは?

(国際連盟の半公式紋章 出典:Wikipedia)
1920年の国際連盟発足以来、日本は常任理事国を務めていました。
また、ヨーロッパから遠距離に位置していることからヨーロッパ諸国の紛争に公平な第三者として需要な立場を担っていました。
しかし、1931年から33年の日本の満州侵略戦争(満州事変)が起こると、これに抗議する中華民国は国際連盟に提訴をします。
連盟はリットン調査団を派遣し「リットン報告書」において、満州事変は正当防衛ではないこと、満州を中国に返還することなどを記します。
これを基に1933年2月24日、国際連盟特別総会で最終的な同意確認が行われ、賛成42票、反対1票(日本)、棄権・不参加各1票で条件が成立。
この直後当時の日本全権であった松岡洋右は「日本政府は連盟と協力する努力の限界に達した」と立場を明確にし、会場を去ったのでした。

(松岡洋右 出典:Wikipedia)
そして同年3月27日、日本は国際連盟脱退を正式に表明。同時に脱退に関する詔書が発布されましたが、1935年までの猶予期間中、日本は常任理事国の分担金を払い続けます。
正式脱退後も国際労働機関への加盟、国際警察活動へ協力など一定の協力関係は保たれていましたが、1938年に日本は日中戦争などの影響もあり「連盟諸機関に対する協力」を廃止。
第二次世界大戦において多くの国の「敵国」となりました。
【日本の国際連盟脱退の語呂合わせ】年号(1933年)の覚え方!

日本の国際連盟脱退の語呂合わせ①
引くさざ(1933)波のように国際連盟から脱退
立場が明確になった途端に退場しました。
日本の国際連盟脱退の語呂合わせ②
行く(19)よさっさ(33)と国際連盟脱退
結論が出たら脱退するのは早かったですね。
日本の国際連盟脱退の語呂合わせ③
聞く耳(1933)持たずな日本は国連脱退
自分たちが正しいと思っていたのでしょうね。
日本の国際連盟脱退の語呂合わせ④
いくさ(戦)見(1933)せたら国連脱退へ
満州事変が原因で脱退に至りました。
日本の国際連盟脱退の語呂合わせ⑤
満州行く(19)と散々(33)な目に遭い、国連脱退
出征させられた人たちは大変だったことでしょう。
以上、日本の国際連盟脱退年号の語呂合わせでした!