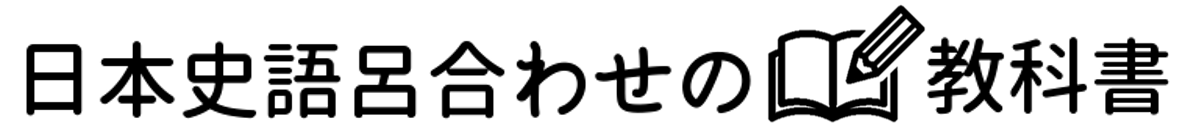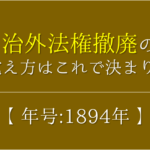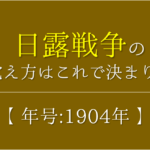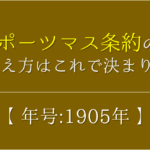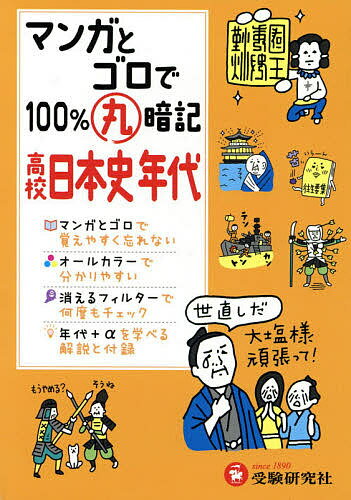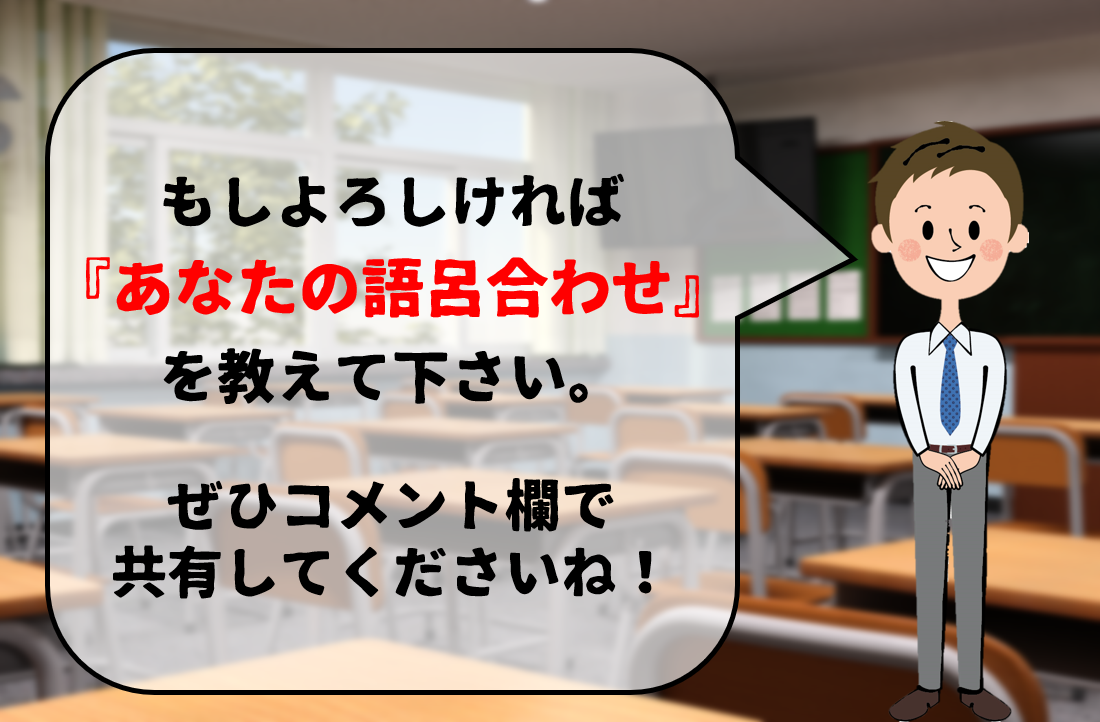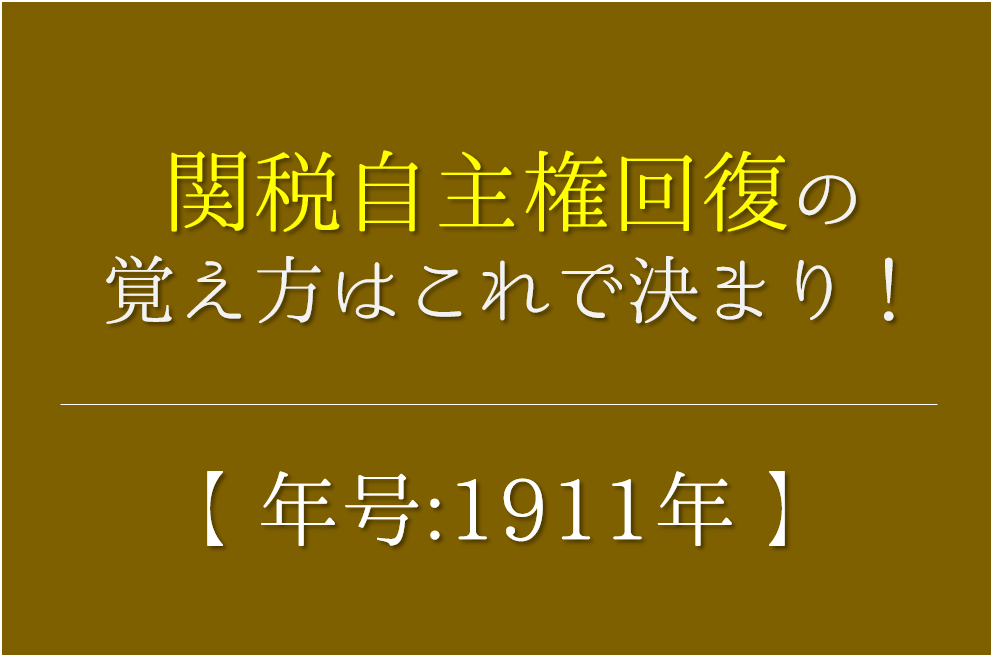
明治政府にとって長年の悲願が幕末に欧米諸国と結んだ不平等条約の「条約改正」でした。
今回はついに悲願達成となった関税自主権の回復について、その概要と年号の覚え方(語呂合わせ)をご紹介します。
目次
関税自主権の回復とは?

(小村寿太郎 出典:Wikipedia)
関税自主権の回復とは、1911年(明治44年)に外務大臣・小村寿太郎がアメリカとの条約に調印したことで完全に回復した関税に関する日本の権利を指します。
幕末に結んだ不平等条約の中で政府を悩ませていたのが「外国に治外法権を認め自国に関税自主権がない」ということでした。
治外法権は1894年陸奥宗光が日英通商航海条約に調印し撤廃されましたが、その際も関税自主権は一部にしか認められませんでした。
関税自主権がないということは輸入品に対しての税率を改訂しようと思っても他国の同意がないと決められないということでした。
例えば輸入品にかける関税が安くなるほど価格も安くなり国産品は売れなくなります。
これでは経済が弱体化し国力も落ちてしまいますね。
財源の確保ひいては富国強兵のためにも関税自主権の回復はとても重要だったのです。
このような状況の中で日本は大国ロシアに日露戦争で勝利、欧米諸国に大いなる驚きを与えました。
そこでこの機会を利用して1905年のポーツマス条約全権であった小村寿太郎がアメリカに交渉をはじめます。
そして、ついに1911年「日米通商航海条約」によって関税自主権の回復がなされたのです。
【関税自主権の回復の語呂合わせ】年号(1911年)の覚え方!

【関税自主権回復の語呂合わせ①】
ひどく(19)いい(11)関税自主権の回復
国内産業の発展や経済にとって関税自主権の回復はいい兆しとなりました。
【関税自主権回復の語呂合わせ②】
関税自主権の回復で低い(191)位置(1)から同じ位置へ
治外法権の撤廃や関税自主権の回復でいよいよ日本も欧米列強国の仲間入り、「脱亜入欧」へと進んでいきます。
【関税自主権回復の語呂合わせ③】
関税自主権の回復とかけて一句(19)いい(11)?
見事に関税自主権を回復させた外務大臣・小村寿太郎、歌を詠みたいほど嬉しかったのでは?
以上、関税自主権回復の語呂合わせでした!
ちょっと裏話
治外法権の撤廃に尽力した陸奥宗光と関税自主権の回復に成功した小村寿太郎は外務省での上司と部下の関係でした。
上司であった陸奥宗光は部下である小村寿太郎の能力を大変に評価し引き立てていたといいます。
この外務大臣2人がいなければ条約改正はもっと遅れていたかもしれませんね。