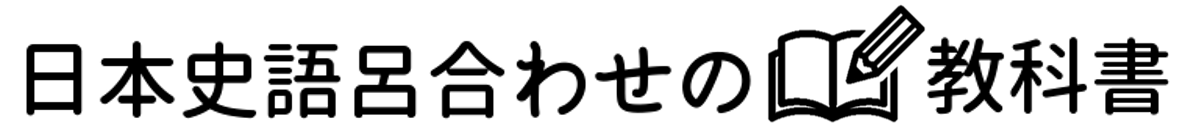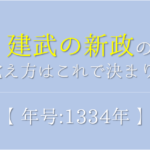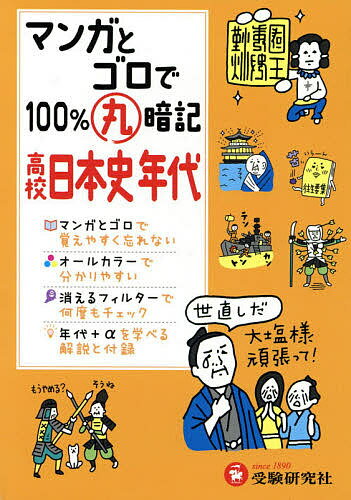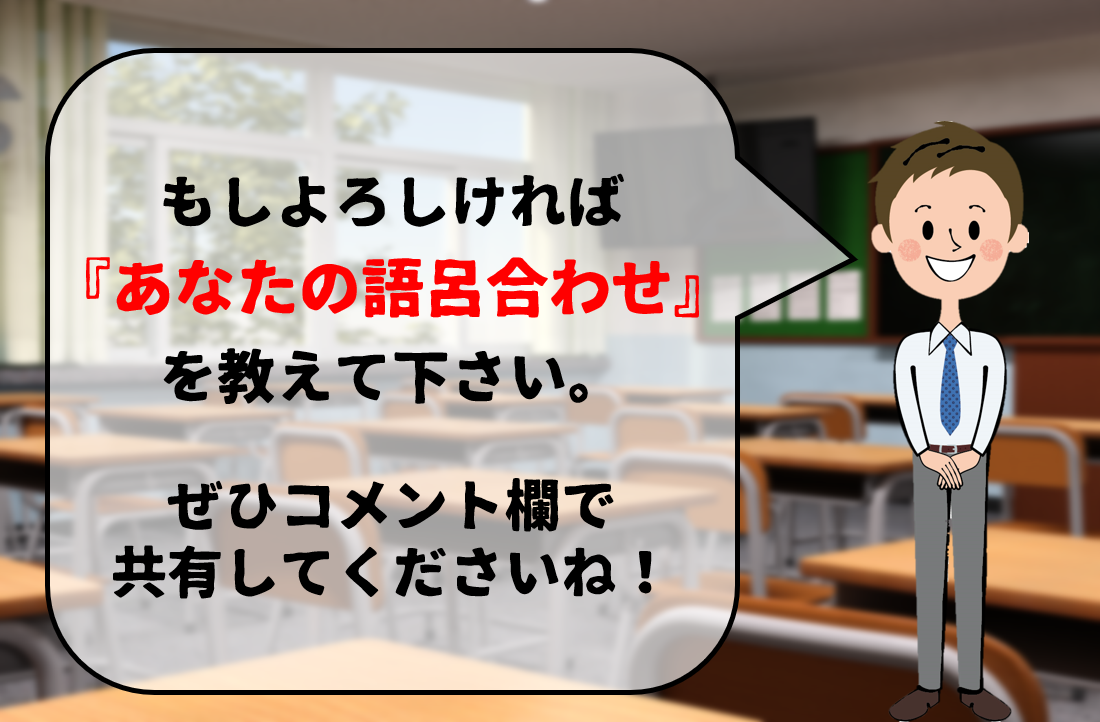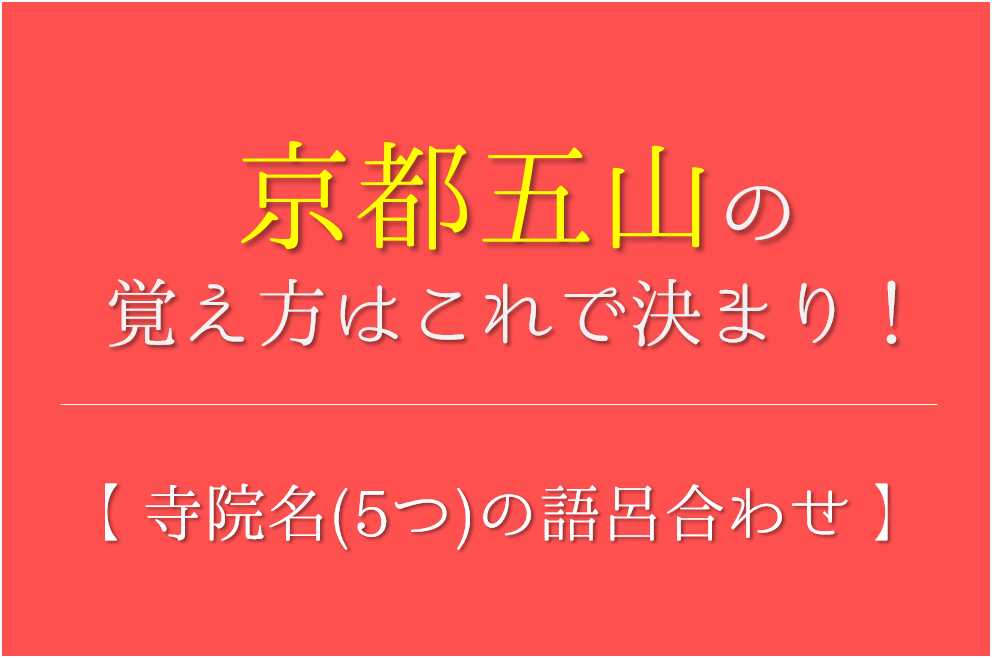
現代ではあまり考えられないことですが、近世までの日本においては寺院が政治に強い影響力をもっていました。
寺院の力を支配しコントロールすることは、政権の上に立ちその権力を維持しようとする者にとって非常に重要なことでした。
そんな政策の一環としてつくられた京都五山の概要・その覚え方についてご紹介していきます。
京都五山とは?

(京都五山の一つ「天龍寺」 出典:Wikipedia)
京都五山とは、南宋の制度にならって鎌倉末期から徐々に作られ、室町時代の足利義満によって制度のことで、京都の寺院のなかで最高の寺格にある五つの禅寺のことです。
具体的には上の順位から天龍寺、相国寺、建仁寺、東福寺、万寿寺の五つのことを指します。
鎌倉時代の末期に北条氏が南宋の制度に倣って、五山制度を導入し鎌倉の寺院を五山に認定していましたが、建武の新政を経て室町幕府になると、京都の寺院を中心に五山が選定されるようになりました。
室町幕府三代将軍の足利義満のときに相国寺を建立し、第一位が天龍寺、第二位が相国寺、第三位が建仁寺、第四位が東福寺、第五位が万寿寺として京都五山としました。
義満の意向で天龍寺と相国寺の順位の入れ替わりなどがありましたが、すぐに戻され、現在まで上記の順位で伝わっています。
また鎌倉五山を別に設け、その両五山の上に別格上位としてそれまでの五山筆頭であった南禅寺をおくことになりました。
五山はいずれも臨済宗の寺院で、官寺として扱いました。
また僧録制度を敷き、官寺の住職の任命権を幕府が掌握するなど、寺院を幕府の支配体制化に置き、その力をコントロールすることに成功しました。
【京都五山の覚え方】簡単!語呂合わせ

京都五山の語呂合わせ①
天から愛する国を建てに東へ行ったがなぜか饅頭を食べた
天(天龍寺)から愛する国(相国寺)を建(建仁寺)てに東(東福寺)へ行ったがなぜか饅頭(万寿寺)を食べた
もともとの目的を忘れて、違うことをしてしまうことはよくありますね。
京都五山の語呂合わせ②
天龍さんは壮行会で役を兼任し、豆腐と饅頭を食べた
天龍(天龍寺)さんは壮行(相国寺)会で役を兼任(建仁寺)し、豆腐(東福寺)と饅頭(万寿寺)を食べた
天龍さんはプロレスラーの天龍源一郎さんをイメージしてください。
京都五山の語呂合わせ③
天国で建てた福を呼ぶ卍
天(天龍寺)国(相国寺)で建(建仁寺)てた福(東福寺)を呼ぶ卍(万寿寺)
天国にもお寺は存在するのでしょうかね。
以上、京都五山の語呂合わせでした!